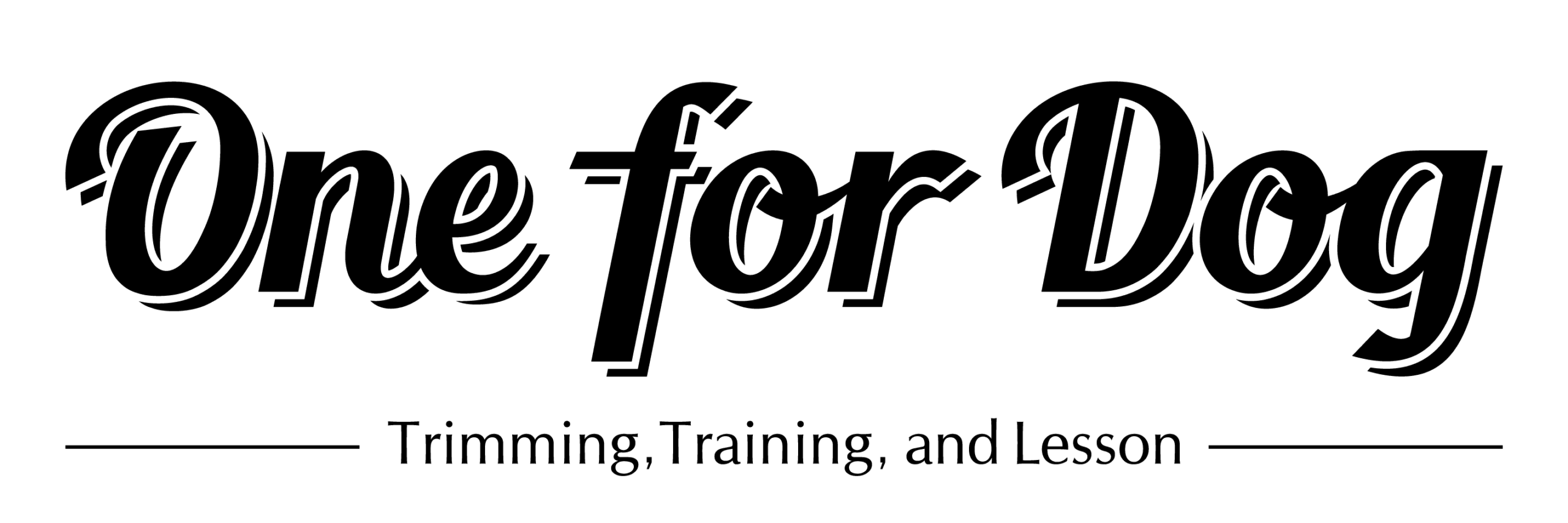先日、お客様とこんな会話がありました。
「なんだか、少し痩せましたよね。あと、お腹ゆるかったりしました?」
トリミング中、肛門まわりの荒れが気になり、お迎えの際に聞いてみたんです。
すると飼い主さんは、少し申し訳なさそうにこう話してくれました。
「実は、ちょっと下痢が続いていて……」
「病院には行きました?」
「それが…病院が本当に苦手で。前に連れて行ったとき、暴れてしまって血尿が出てしまって…結局、診察もままならずに帰されてしまったんです」
治すために行った病院で、かえって状態が悪くなってしまった。
この話を聞いてしまうと、簡単に「無責任な飼い主」とは言えません。
とはいえ、このままでいいはずもない。
「セカンドオピニオンは考えました?」
そう聞くと、飼い主さんは少し戸惑った様子で答えました。
「いえ…ずっと、いつもの先生にしか…」
そもそも、動物病院は“嫌われやすい場所”
これは前提として知っておいてほしいのですが、動物病院という場所そのものが、犬にとってはかなりのハンデを背負っています。
体調が悪くなってから行く場所。
診察台に乗せられ、体を押さえられ、触られ、注射をされる。
人間はこう思います。
「治してくれる場所でしょ?」
でも、犬からすればそんな理屈は通じません。
「こんなに具合が悪いのに、なんでこんなことされるんだ!」
そう思っても不思議ではありません。
たとえ予防接種であっても、痛い思いをする場所はやっぱり嫌な場所です。
だからこそ必要なのが、“耐性づくり”。
ドッグトレーニングでよく使われる言葉でいうと、「脱感作」や「系統的脱感作」という考え方です。
- 脱感作
触られても嫌がらないように、ごく弱い刺激から少しずつ慣らすこと - 系統的脱感作
ご褒美とセットにして、刺激を受け入れられる範囲を広げていくこと
ざっくり言えば、
「多少揉みくちゃにされても、尻尾を振っていられる犬に育てよう!」
そんな感じ。
#説明が雑っ!
私たちはつい、背中や頭など触りやすいところばかり撫でがちです。
でも本当に慣らしておきたいのは、将来“嫌がりやすい部位”。
「お手」「おかわり」は、芸というより、前肢という急所を触らせる練習でもあります。
それができたら、次は「他人にも触らせる」。
こうして少しずつ順化していくことが、本来のしつけ。
問題行動を直すためだけが、しつけではありません。
“不快の種”を減らしてあげること。
その延長線上に、診察があります。
一度貼られた“レッテル”は、なかなか剥がれない
では、今回のケース。
飼い主さんはどうするべきなのでしょうか。
結論から言います。
「レッテルを避ける」ことです。
犬の頭の中では、こんな連想が起きています。
- 獣医さんは嫌なことをする
- 嫌なことをされる診察台が嫌
- 診察台のある診察室が嫌
- 診察室のある病院が嫌
- 病院へ向かう道も嫌
こうして一度レッテルを貼られた病院は、犬にとって「理屈も慰めも通じない場所」になります。
ここまでくると、脱感作でどうにかなるレベルを軽く超えてしまう。
飼い主さん自身も、実はそれを薄々感じています。
だからこそ、悩んでいるんですよね。
「かかりつけ医」は、絶対じゃなくていい
なぜか日本では、「かかりつけ医」という言葉がとても強く響きます。
「先生がそう言っていたから」
その言葉を、ほぼ絶対視してしまう。
でも、少し人間社会に置き換えてみましょう。
皮膚科の先生に腹痛を診てもらいますか?
内科の先生に虫歯を治してもらいますか?
――しませんよね。
餅は餅屋。
医師の側だって、専門外であればこう言います。
「それは専門の先生に診てもらってください」
ところが動物医療の世界では、日本は二次診療施設が極端に少ない。
そのため、犬も猫もウサギも、皮膚も眼も腫瘍も、なんでも診るのが“当たり前”になっています。
でも、「やる」と「できる」は別の話。
欧米では、内科・外科・皮膚科・腫瘍科・循環器科・神経科・歯科…
細かく専門医が分かれています。
私たち業界側は、状況に応じて病院を使い分けます。
「ワクチンはこの先生」
「整形外科ならこの先生」
同業だと分かれば、獣医師側から紹介されることも普通です。
それなのに、一般の飼い主さんほど、セカンドオピニオンを「遠慮」してしまう。
一方で、獣医師にもプライドと責任があります。
「診てください」と言われれば、当然診ます。
ただし、すべての高度医療を一人で完璧にこなせるわけではありません。
だから――
セカンドオピニオン、大いに結構。
結論は、驚くほどシンプル
さて、冒頭の話はどうなったのか。
結論はとてもシンプルです。
愛犬にレッテルを貼られてしまった病院に、無理やり通う必要はありません。
ということで、選択肢はひとつ。
「印象のない、別の病院へ行く」
これに尽きるわけですな。
#2行で済む話!